


個人事業主になると、税金も自分で確定申告をして納める必要があります。
その際にどのような税金を納めることになるのか、ご存知でしょうか?
基本的に、納めることになる税金は主に4種類となっているのですが、それぞれどのような税金なのか解説します。
主に支払うのは所得税
個人事業税が納める税金は、主に4種類あります。
その中でも特に大きいのが、所得税です。
その計算方法は、どのようになっているのでしょうか?
所得税は、1月から12月までの1年間で事業によって所得を得た場合に納める義務が生じる税金で、納める金額は所得額によって変わります。
そして、その割合も変わってくるのです。
所得は、売上を基準としてそこから認められた控除、および事業にかかる経費を差し引いたものです。
所得税は累進課税という制度で計算されています。
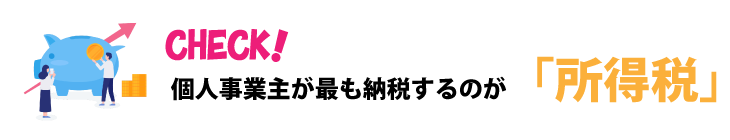
累進課税は、所得の金額が大きければ大きいほど、税率も大きくなるというものです。
例えば、所得が195万円以下なら、税率は5%で控除はありません。
しかし、そこから税率と控除額は段階的に増えていき、4000万円を超えている場合の税率は45%となり、479万6千円の控除を受けることができます。
会社員の場合も所得税はかかりますが、その場合は毎月の給与から天引きされます。
しかし、個人事業主は天引きされないので、毎年2月から3月半ばまでの間に確定申告をして、所得税がいくらになるのかを自分で申告しなくてはならないのです。
そして、その金額を税務署や金融機関、口座振替などで申告の期限日までに納めなければなりません。
忘れた場合は延滞税が加わり、納付する金額が増えてしまうので注意しましょう。
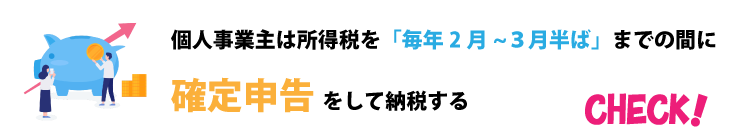
また、所得税を納付する際は、合わせて復興特別所得税も納付します。
これは、東日本大震災の復興対策の財源となるもので、所得税額を基準としてその2.1%となっています。
その他の3つの税金
その他の税金もあるのですが、その中で現在特に注目されているのが消費税です。
消費税に関しては、年間の売上が1,000万円以下の個人事業主であれば免税事業者として納付を免除されることも可能です。
しかし、2023年10月からはインボイス制度が開始されるため、免税事業者のままではいられなくなる可能性があります。
どちらにするのか、制度の開始までには決めておきましょう。
消費税は、基本的に受け取った消費税をそのまま納めるだけです。
標準税率の場合、10%中7.8%が国税となり、2.2%が地方税となります。
軽減税率の場合は、6.24%が国税になり、1.76%が地方税です。

地方自治体に住民として登録している以上、住民税も納める必要があります。
住民税は、住所のある都道府県、並びに市町村へと納めます。
確定申告をすると住民税課税決定通知書が送付されてくるので、年4回に分けるか一括で納付します。
特有の税金が、個人事業税です。
これは、個人事業主の中でも特定の事業を行っている人が納付する義務のある税金で、保険業や医業、コンサルタント業など合計70業種が該当します。
納付する額は、所得を基準に計算されます。
第1種事業に分類されている業種では5%、第2種事業の場合は4%、第3種事業であれば5%もしくは3%となっています。
こちらの税金も、住民税と同じく確定申告をすると税務署から自動的に納税額通知と納付書が送付されます。
また、1年間で290万円の控除があります

まとめ
個人事業主になると、会社員の場合は意識する必要がない税金の納付義務を負うことになります。
個人事業主が納める税金は4種類あるので、それぞれどのようなときに納める必要があるのかを把握しておきましょう。
また、消費税と個人事業税は租税公課に当たるため、経費として計上することが可能です。
損をすることがないように、税金について学んでおきましょう。
一般社団法人全日本ビジネスマーケティング協会
〒 104-0061
東京都中央区銀座一丁目22番11号
銀座大竹ビジデンス2階
